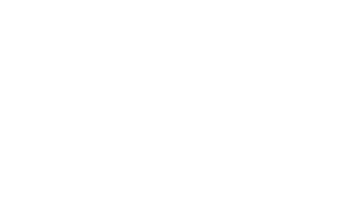プロジェクトの目的
このプロジェクトでは、土器の胎土や付着炭化物など、考古学資料に残留する脂質分析を学内共同利用として委託分析を行います。博物標本として学術的な価値を有する考古学資料から、最小限の棄損で最大の情報を抽出する方法を探求します。また考古学者と対話を通じて、分析データの文化的・社会的な意義を明らかする、新たな文理融合領域「ミューゼオメトリー」の確立を目指します。
プロジェクトの概要
【実施期間】2025~2026年度
【実験室】浅野キャンパス・タンデム加速器研究棟(MALT)3階
【構成員】PI:米田穣(東京大学総合研究博物館放射性炭素年代測定室教授)
PI:松崎浩之(東京大学総合研究博物館タンデム加速器分析室教授)
特任研究員:宮田佳樹・小澤仁嗣
学術専門職員:宮内信雄・川本万理奈
委託分析について
脂質分析プロジェクトは、総合研究博物館が新たに提供する学内共同利用事業です。東京大学の教員や学生が参加しているプロジェクトでも利用して頂くことが可能です。測定に対する潜在的なニーズを調査し、定常的な運営にむけた適正な測定実費を評価するために、測定実費をお支払い頂いて試験運用しています(2026年度まで)。学外の研究プロジェクトについては、当プロジェクト構成員との共同研究として、ご利用頂くことも可能です。学術利用を目的としたプロジェクトのため、科学研究費などの公的研究費でお支払い下さい。
共用事業について
民間企業などで公的研究費によらない測定を希望される場合は、共用事業として分析を実施可能です。共用事業は、高度な分析技術と装置を学術研究を超えて広く活用して頂くための事業です。測定経費は学術目的の委託分析とは異なりますので、ご了承下さい。共用事業については、メールにて個別にご相談下さい。
問い合わせ先:lipid@project.um.u-tokyo.ac.jp
委託分析の内容
- 残留脂質分析:①前処理(酸抽出法)、②脂質量測定(GC)、③バイオマーカー測定(GC-MS)、④個別脂肪酸の炭素同位体比測定(GC-C-IRMS)
- 全脂質抽出オプション:①前処理(前脂質抽出法)、②脂質量測定(GC)、③バイオマーカー測定(GC-MS)
- 炭素・窒素同位体比測定オプション(EA-IRMS)*
* 炭素・窒素同位体比測定のみでの依頼は別途ご相談下さい。
測定実費
| 項目 | 内訳 | 測定実費(税込) | |
| 学内共同利用 | 共用事業 | ||
| 残留脂肪酸分析 | 前処理(GCによる確認を含む) | 20,000円 | 40,000円 |
| GC-MS | 10,000円 | 20,000円 | |
| GC-C-IRMS | 10,000円 | 20,000円 | |
| クロロフォルム・メタノール抽出 オプション | 前処理+GC-MS | 20,000円 | 40,000円 |
| 炭素・窒素同位体オプション | EA-IRMS | 5,000円 | 10,000円 |
委託分析の申し込み
- 事前に構成員との相談をお願いしております。プロジェクトのメールアドレス(lipid@project.um.u-tokyo.ac.jp)にお問い合わせください。
- 分析試料は東京大学まで送付して下さい。現地採取が必要な場合はご相談下さい。
- 土器胎土の分析には資料の破壊が伴います。必ず資料管理者・機関から正式な分析許可を取得してください。
- 測定結果の報告まで、お申込みから4カ月程度かかります。測定の申し込みや機器の不調などによっては、納期が変更になる場合もございますので、ご了承ください。
- プロジェクト構成員との協議終了後に、こちらの確認書(Googleフォーム)に入力をお願いします。資料と確認書の受領をもって契約完了といたします。
残留脂質分析について
脂質分析では、土器胎土あるいは土器付着炭化物に残留する脂質を分析し、土器に貯蔵あるいは加熱された成分を推定します。特定の素材に由来する成分(バイオマーカー)の分析から、水産物やキビ、蜜蝋などの成分を検出できます。また主な脂肪酸2種(パルミチン酸とステアリン酸)の炭素同位体比を測定することで、脂質が主に由来した成分を推定することができます。通常は、脂質の量を多く回収することができる酸抽出法を実施しますが、比較的壊れやすい成分(デンプン由来の成分など)を分析するために、全脂質抽出法で前処理することも可能です。
土器の胎土には多くの脂質が残留しますが、どのくらいの時間幅の情報を反映しているか、不明確です。また土器を一定量破壊する必要があります。一方、土器付着炭化物は、比較的短い期間(1回から数回の加熱料理)の情報を反映すると考えられます。土器本体は破損しませんが、かなり多量(100mg以上)の炭化物を必要とするので、分析できる資料が限られます。どちらの試料でも、含まれる脂質量が十分でない場合には分析結果が得られません。それぞれの資料の特徴をよく理解して、研究計画を立案して下さい。
画像提供:函館市縄文文化交流センター